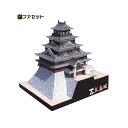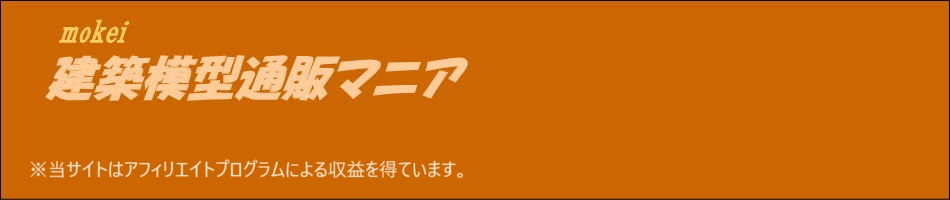-
建築模型通販マニア
-
ペーパークラフト ファセット 日本の名城シリーズ 広島城 1/300(3) 購入
ペーパークラフト ファセット 日本の名城シリーズ 広島城 1/300(3)の購入ページです。
ペーパークラフト ファセット 日本の名城シリーズ 広島城 1/300(3) 購入
- ペーパークラフト ファセット 日本の名城シリーズ 広島城 1/300(3)
-
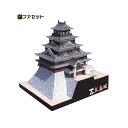
ペーパークラフト ファセット 日本の名城シリーズ 広島城 1/300(3)
1,100円
|
日本各地のお城を紙で作るペーパークラフトシリーズです。 中国地方の覇者、毛利元就の孫の輝元が築城した広島城を1/300サイズのペーパークラフトとして再現しました。 商品名:広島城 ペーパークラフト 日本名城シリーズ1/300 対象年齢:中学生以上(器用な方にお勧め!) 作成時間:5〜8時間(個人差があります) 完成サイズ:横15.0×奥14.0×高15.5cm(実物の1/300スケール) 商品仕様:A4部品図×4枚、組立図×2枚 ※製造時期により、内容品構成の枚数が変わる場合があります。 ※注意:本品は切り込み加工は施してありません。 ※メール便でポストへのお届けです。 地域によって発送後2日から4日かかります。 【用意するもの】 ・ハサミ、カッター、カッターマット、定規、ピンセット ・接着剤(クラフト用のりや木工用ボンド) ・先のとがったもの(折り目を付けるために使用) ・爪楊枝(細かな場所に接着剤をつけるときに使用)【作成時のご注意】 ・すべての部材に切り込み・折れ目の圧縮の加工はされておりません。 ご自分で部材の切りだし、折れ目加工は行ってください。 ・接着剤の塗りすぎに注意。 塗りすぎると、水分が紙に浸透することで撚れが生じます。 ・接着前にのりしろ部分の折り目はきっちりと折っておくこと。 【広島城の歴史】 ■広島城は中国地方9ヶ国112万石となっていた毛利輝元により5重5階の複合連結式望楼型天守として建てられました。大天守の東と南に小天守を持ち、渡櫓で繋がれていました。 望楼型の天守は黒漆塗りの下見板が張られ、豊臣秀吉の大坂城に似せて作られたと言われます。屋根には金箔瓦が使用され、荘厳な姿をしていたと言われますが、内部は天井も張られていない簡素な天守でした。 ■天正17年(1589)に築城が開始されました。川の中州の埋め立てと堀の浚渫という大工事を行う事から始まり、城の構造は大坂城を、縄張りは聚楽第を参考に作られました。 豊臣秀吉の文禄の役と同時期で、後方基地としての期待もあり築城のサポートとして、黒田如水を派遣したり、建設中の広島城へ滞在したという話も残ります。 ■関ヶ原の合戦の後、慶長5年(1600)に2ヶ国に減封された毛利輝元に代わり、福島正則が入城しました。正則は、城の北側を通っていた西国街道を城下の南側を通るように変更すると共に、雲石街道を整備しました。それによって町人町が拡大しました。 しかし、幕府に無届けで修築したため、とがめられて二段あった本丸の上段石垣を破却しました。その名残を現存でも確認する事ができます。 元和5年(1619)改易になった正則に代わり入城した浅野氏が、明治まで12代250年間居城としました。 ■明治期に小天守を失い、大天守のみが保存される事になり、戦前は他の現存する建物と共に旧制の国宝に指定されました。 太平洋戦争の原爆投下により、爆発時の熱線に耐えましたが、直後の爆風によって倒壊し、大量の建材が天守台や北側の堀に散乱したと言います。 昭和33年(1958)に現在の大天守が復元され、平成元年(1989)から二の丸などいくつかの建造物が木造で復元されました。 【広島城の歴代城主】 初代毛利輝元天正19年(1591)−慶長5年(1600) 二代福島正則慶長5年(1600)−元和5年(1619) 三代浅野長晟元和5年(1619)−寛永9年(1632) 四代浅野光晟寛永9年(1632)−寛文12年(1672) 五代浅野綱晟寛文12年(1672)−延宝元年(1673) 六代浅野綱長延宝元年(1673)−宝永5年(1708) 七代浅野吉長宝永5年(1708)−宝暦2年(1752) 八代浅野宗恒宝暦2年(1752)−宝暦13年(1763) 九代浅野重晟宝暦13年(1763)−寛政11年(1799) 十代浅野斉堅寛政11年(1799)−天保2年(1831) 十一代浅野斉粛天保2年(1831)−安政5年(1858) 十二代浅野慶熾安政5年(1858)−在任5ヶ月後に卒去 十三代浅野長訓安政5年(1858)−明治2年(1869) 十四代浅野長勲明治2年(1869)−明治2年(1869)
■森のこびと
レビュー件数:0
レビューアベレージ:0
|
- PR
-